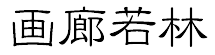小池 昌弘
略歴
こいけ まさひろ
1955 岐阜県下呂市萩原町生まれ
1987 渡仏
1988 仏 ル・サロン入選
1990 仏 ル・サロン入選
1992 仏 ル・サロン栄誉賞
ル・サロン栄誉賞作品
1997 パリ ギャラリー ロマネにて個展
「ル ド セーヌパリ」 以降 取り扱い
2000 仏 サン ポール ド ヴァンス
ギャラリーメデテラネ 取り扱い
2003 ロンドン大学 ロイヤル ホロウェイ
カレッジ買い上げ
2012 大阪 梅田画廊にて個展
2013 名古屋 画廊若林にて個展
現在 パリ在住 無所属
 ジェネラル ルクレール大通り(パリ)12F
ジェネラル ルクレール大通り(パリ)12F
小池昌弘――人・作風・作品
独学の人
 冬の街角(パリ) 12F小池さんは師を持たず、専門教育も受けずに画家となった人です。
冬の街角(パリ) 12F小池さんは師を持たず、専門教育も受けずに画家となった人です。
正真正銘、独学の人ですが、唯一の例外がグラン・シュミエール(パリ)通いです。
百年の歴史を誇る画塾で、かつてシャガールや佐伯祐三も学んだ名門です。
短期間ながらここでの実技体験から、決定的とも言える影響を受け、画家として開眼できたとのこと。
端的にいえば敬愛してやまないレンブラントの再発見と再認識です。
なぜあれほど光を巧みに操れるのか?
なぜあれほど自己の内面を作品に写し込めるのか?
そう問いかけながら教室で絵筆を動かし続けているうちに、ある日、オランダ絵画の巨匠が秘めた創作の秘密が、なぜかふっと理解できたような気がしたと言います。
その感動の一瞬を「体のどこかでスイッチが入った」と語る小池さん、かくして画家としての針路がピタッと定まります。
すなわち、<レンブラントを源流とする欧州のクラシックになんとしてもつながりたい>と。
これを胸に刻んだ小池さん、以降、筋金入りの独学スピリットと飛騨人特有の粘り強さで、写実の道をひたすら一直線に進む日々。
初冬のある日、セーヌ河畔で写生に没頭する小池さんを、その気迫あふれる姿に惹かれたプロカメラマンが撮影、後日、これがパリの観光絵ハガキとして大々的に売り出されたこともありました。
明暗のトーン
 カトリーヌ M20小池作品を前にして「久しぶりに実に絵らしい絵を観た」とその感動を語った人がいましたが、まさに的を射た言葉です。
カトリーヌ M20小池作品を前にして「久しぶりに実に絵らしい絵を観た」とその感動を語った人がいましたが、まさに的を射た言葉です。
ヨーロピアン・クラシックを範とするだけに、勢い作品が古典的な色彩を強く帯びるのは当然のことです。
事実、なんと反時代的な作品かと評する声も一部で聞かれました。
しかし作品が放つ色彩の重厚さと構成の堅固さ、さらに画面全体をおおうなんとも言えないあの優美さ、こうしたテイストを愛好し称賛する人も多くいることも事実です。
なぜでしょうか。
秘密を解くカギはその技法、つまりレンブラントに学んだ光の技法にあるような気がします。
<光とは、色彩よりもむしろ明暗の度合いの問題なのだ>。
巨匠のこの言葉を毛穴から沁み込ませてキャンバスに向かい、その高度な明暗の技法を悪戦苦闘しながら自分のものにしたと聞いています。
まず事物を光と影としてとらえ、次にその明暗の諧調を整え、そして最後に必要な色を塗っていく。
つまり<明暗のトーンに色彩を従属させること>、これこそ小池絵画の真骨頂といえます。
ご本人が好んで描くパリ風景、その空、雲、舗道、壁、屋根などの色調に、えも言われない深みが感じられるのはそのためです。
小池さんのこの秀逸な技法にも目を向けて、作品をじっくり鑑賞していただきたいと思います。
プチ・ブールバーァル派
 サンミッシェル P6パリの町並みと言えば、印象派の作品が広く知られていますが、小池作品はそれらとはずいぶん趣きを異にします。
サンミッシェル P6パリの町並みと言えば、印象派の作品が広く知られていますが、小池作品はそれらとはずいぶん趣きを異にします。
色彩はあくまでも抑制的で、描く対象も多くは下町風景です。
<初めに色ありき>の印象派の生き方に対して、小池さんの立場は<色は明暗の度合いに従うべし>、そもそも方向が違うからこれはやむをえません。問題は描く対象の場所です。
印象派の画家たちがシャンゼリゼに代表される大通り(ブールバァール)に目をむけ、カフェやブチックを明るく華やかに描きました。
これとは対照的に、小池さんが関心を寄せるのは、もっぱらセーヌ左岸の庶民的な小路や露地です。
表通りの華やぎはないものの生活の確かさが息づく、いわばプチ・ブールバァール、これこそが小池さんにとっての本当のパリなのでしょう。
小路の角を彩るカフェ、裏通りに面したパン屋、路地の一角を占める花屋・・・ていねいに描き込まれたキャンバスからは、客同士の会話や店主の風貌までが伝わってきそうです。
一言でいえば<奥行きのある深い絵>。
それを裏付けるように小池さんはこう語っています。
「壁や窓の向こうには部屋があり、そこには必ず人間の暮らしがあります。
その生活感までも描き込みたいと思う。」
田島一郎